「あの8日間が、価値観を変えた」——若手社員が語るミラノサローネ視察記
「行かないと絶対に後悔する」
ミラノサローネ2024で出会った、デザインという新しい世界
2024年春、ADIは初の海外視察として、代表取締役CEOの木本をはじめとする7名で、イタリア・ミラノで開催された世界最大級のデザインイベント「ミラノサローネ」を訪れました。
全社的なデザイン力の底上げを図るため、最新のインテリアデザイン動向の把握や、今後の開発・設計におけるスタイルの拡充を目的とした本研修。社内公募で選ばれた4名の若手社員が、それぞれの視点で「デザインと向き合った」経験を語ります。
今年春に予定されている第2回ミラノサローネ研修の実施を前に、改めて前回の体験と学びを振り返り、その価値を社外にもお伝えしたいと考え、本記事の公開に至りました。

—伊橋さんの場合
「カタチにする」からこそ、デザインを学びたかった
率直に言って、会社の業務で海外に行けること自体が嬉しかったんです。しかも建築に関わることだなんて、これ以上ない機会でした。ただ、他の3人と違って私だけが工事課所属で…周囲からは「デザインと直接関係ある部署なの?」と思われそうですよね。実は私自身も、最初はそう感じていました(笑)。
どのような思いで応募されたのでしょうか?
私たち工事課は、「このデザインを実現したい」「こんな空間をつくりたい」といった想いを、実際の“カタチ”にしていく役割です。でも、クリエイターの方の意図を深く理解していないと、本当に伝えたいものを再現するのは難しい。だからこそ、現場にいる私たちにもデザインを学ぶ機会が必要だと思い、応募しました。
とても興味深い視点ですね。そうした考え方は、普段の業務や研修を通じて培われたものなのでしょうか?
部署内での勉強会は時々ありますが、他部署と連携して学ぶ機会は正直あまり多くありません。でも、新しいことを学ぶのが好きなので、そうした機会があれば積極的に参加したいと思っています。
(他のメンバーに向かって)皆さんの部署では、部署を越えた学びの機会はありますか?
私たちの部署は比較的恵まれていると思います。メーカー主催のセミナーが年に2~4回ほどあり、社内ポータルから申し込めば誰でも参加できます。ただ、どちらかというとデザイン講座というよりは、自社製品のプレゼンテーションに近い内容ですね。あとは、毎年6〜7月頃に各メーカーがミラノサローネの報告会を開催しています。商材以外にも、マーケティング系のウェビナーもよく視聴しています。
□実際にミラノサローネを体験して
本当に衝撃的でした。世界中のクリエイターたちが「何をつくりたいのか」という、その根源的な部分に触れられて。普段は「何をつくるか」を考える人と「どうやってつくるか」を考える人で役割が分かれがちですが、今回は「何をつくるか」を突き詰める人たちの視点を肌で感じられて、とても刺激になりました。
工事課としての専門性を持ちながら、デザインの本質も捉えようとしている姿勢が伝わってきます。現地での体験で、事前のイメージとのギャップはありましたか?
想像以上に、一つ一つの作品が“深い”んです。単に「おしゃれな椅子をつくろう」といった表層的なものではなくて。たとえば、創業100年を超える企業が、時代との対話を重ねながら得たインスピレーションを基に、ようやく生まれた一脚の椅子…そんな背景が込められている作品が多くて。その深さに圧倒され、「自分にはこのレベルには届かないのでは…」と不安になった瞬間もありました(笑)。
(笑)それは現地に着いてから感じたことですか?
実は、事前レポートを読んだ時点で、すでにそんな気持ちになっていました(笑)。
□ミラノサローネ、その瞬間
現地に到着して、「ミラノサローネに来た」と実感した瞬間はありましたか?
駅に降り立った時から、すでに空気が違いました。プラットフォームのあちこちにポスターが貼られていて、パンフレットを配る人もいて。しばらく天井の低い通路を進むと、突然視界が開けて、印象的なガラスの屋根と垂れ幕が目に飛び込んできて…。「ついに来た!」という高揚感が一気にこみ上げてきたのを、今でもはっきり覚えています。
電車の中でも、カラフルな装いの人や、デザイナーらしい雰囲気の方がたくさんいて。その空気感そのものが、すでにミラノサローネの世界観に引き込まれていくようでした。

—野中さんの場合
憧れの地へ、背中を押した直感
きっかけは、2023年11月に建築本部宛に届いた一通のメールでした。応募締切はわずか2週間。会社としても前例のない取り組みだったこともあり、提出後に求められるレポートや提案の内容がどの程度になるのか見えず、最初は本当に迷いました。でも最終的には、「行かないことを必ず後悔する」という直感が背中を押してくれたんです。
印象に残っているのは、応募書類の形式に一切の指定がなかったことです。もしかすると、これはデザイン研修ならではの自由度で、表現力や感性が問われているのかな…なんて思って(笑)。むしろ「自由であること」が難しく感じましたね。他の人がどんなアプローチを取るのか分からない中で悩みましたが、私は最もオーソドックスな形式——Wordで「建築本部長殿」から始まる、やや堅めの文書で提出しました(笑)。
後で他のメンバーと話してみると、それぞれの応募方法に個性が出ていて、とても興味深かったです。小林さんは自己プロデュースに特化した資料をまとめていて、宣材写真まで完璧に仕上がっていましたし、伊橋さんは情熱的なデザイン論をA4用紙びっしりに書き綴っていて。本当に、それぞれの想いが表れていたと思います。
□挑戦の先に見えた変化
その経験は、ご自身にどのような変化をもたらしましたか?
一番大きかったのは、「挑戦的な選択」に対する考え方が変わったことです。代表の木本さんが朝礼で「機会の平等」という言葉を使っていたのですが、それが強く印象に残っています。あの研修も、建築本部の誰にでもチャンスは開かれていました。でも、実際に手を挙げた人だけが、その貴重な機会を掴めた。その事実を通じて、「迷ったときこそ挑戦を選ぼう」と思えるようになりました。
□憧れのミラノサローネと、心に残る出会い
ミラノサローネには、以前から関心があったのですか?
はい。数年前、建材メーカーさんのセミナーで、視察報告を聞いたことがあったんです。その時からずっと憧れてはいたのですが、正直「自分が行くことはないだろうな」と思っていました。だからこそ、世界の最前線でデザインを体感できたこの機会には、本当に感謝しています。
実際に現地で、印象に残ったことは?
海外のクリエイターたちが、自社のプロダクトに強い誇りと信念を持っていたことです。「私たちの製品って、素晴らしいでしょう?」と自然に語れる、その自信と姿勢に圧倒されました。それは今の自分にはまだ持てていない部分で…製品に対する誇りを持ち、それを自分の言葉で伝えられるようになりたいと感じました。
□次のステップへ
もしまたチャンスがあれば…?
(笑顔で)はい、ぜひ参加したいです。前回は初めての海外渡航だったこともあり、要領をつかむのに時間がかかってしまいました。だからこそ、今ならもっと成果に結びつく動きができると思っています。事前レポートも、現地での気づきをより活かすような内容にできるはずです。
※なお、2025年4月6日から14日にかけて実施される予定のミラノサローネ研修には、野中さんも再び選抜メンバーとして参加が決定しています。

—森川さんの場合
写真では見えなかった、デザインの本質
ミラノサローネに行かれて、どのような印象を受けましたか?
「出発から帰国まで、ずっと楽しかった!」——それが一番率直な感想です(笑)。同時に、「まさか自分たちが行けるなんて…」という驚きも大きかったですね。デザイン系の企業であれば、現地研修があるところもあると思いますが、当時のADIではまだそこまでデザインに注力できていたわけではありませんでした。だからこそ、「行ってみよう!」と会社が一歩踏み出したことは、とても画期的だったと感じています。
行く前から圧倒されるとは思っていましたが、実際はその想像をはるかに超えていました。目の前に広がる情報量に、思わず言葉を失うほどでした(笑)。
特に印象に残った作品やデザインはありましたか?
多くの展示を見ていく中で、心惹かれるデザインの多くが同じデザイナーの手によるものだと気づいた瞬間がありました。私の場合は、ピエロ・リッソーニさんとパトリシア・ウルキオラさんです。 リッソーニさんのデザインは、直線的でシンプルながら、素材や色で絶妙なアクセントが加えられていて。そのバランス感覚が印象的でした。ウルキオラさんの作品は、どんな色調でも華やかに見える色使いと、やわらかな曲線美が特徴的で…。 写真では伝わらない「にじみ出る魅力」を、現地で体感できたのは本当に大きな収穫でした。
とても森川さんらしい表現ですね。現地では、どのように情報を収集していたのですか?
会場では、基本的にQRコードやポップで詳細情報を確認できるようになっていて、気になった作品をどんどんチェックしていったんです。すると「あ、これもリッソーニさんだ!これも!」と、自然に好みのデザイナーに惹かれていることに気づいて(笑)。 自分の中に、明確な「好き」の傾向があったことを発見できたのは、とても嬉しい気づきでした。
□フォーリサローネに感じた「生きた空間」の魅力
ミラノサローネとフォーリサローネ、それぞれ現地で体験されてみて、いかがでしたか?
ミラノサローネ本会場は、まさに「祭典」という感じで、お祭りのような高揚感がありました。私も1日目からテンションがぐっと上がって(笑)。 でも、個人的に特に惹かれたのは、2日目・3日目に訪れたフォーリサローネでした。街なかで、より実空間に近いスケール感で展示されていて、光や空気感、周囲の建物や街並みといった要素がすべて混ざり合って、「ブランドの世界観」がそのまま空間として伝わってくるんです。 展示会場では味わえない、リアルで生きたデザインの力を感じられる体験でした。
□デザインとは、「理念をカタチにする」こと
森川さんは、今回の参加メンバーの中で唯一デザイン室の所属でした。現地での経験は、今後どのように活かされそうですか?
まず、現地で得たトレンドや空気感は、リブランディングの取り組みにも反映しやすく、今後さらに活用の幅が広がっていくと感じています。他社がプロダクトへの落とし込みを検討している段階でも、私たちはいち早く動き出せる、そんな実感を得ることができました。
それと、改めて「デザイナーとは何か」を考えさせられました。どのデザイナーも複数のブランドとコラボレーションしているのに、仕上がるプロダクトにはそれぞれ違う“顔”がある。 それはきっと、ただ見た目を整えるだけでなく、その企業の理念や価値観を理解したうえでデザインしているからこそ生まれるものなんだと感じました。
ADIにおいても、これからますますデザインの可能性が広がっていくと思います。今回のミラノでの体験を大切にしながら、私たちらしいデザインを、一歩ずつかたちにしていけたら嬉しいです。

—小林さんの場合
デザインが紡ぐ、次なる一歩
サローネや出展ブランドについては、ほとんど予備知識のない状態からのスタートだったとのことですが、そこからどのように準備を進めていかれたのでしょうか?
具体的な準備の流れをお話しすると、まず取締役の風間さんが選定した146社から、知名度や展示場の所在地を考慮して79社に絞り込みました。その79社を4人で手分けして事前レポートを作成し、現地ではそのうち63社を視察することができました。帰国後の報告会に向けては、さらに12社に厳選し、一人3社ずつを担当する形で取りまとめました。
面白かったのが、事前レポートの段階で「このブランドは有名」とか「このプロダクトは必見」といった情報が出てきても、私たち…正直ほとんど知らなかったんです(笑)。しかも工事課の私だけでなく、全員が!(苦笑) 最初は「軽い気持ちで応募したことを後悔するかも…」と思ったほどですが、調べれば調べるほど興味が湧いてきて。「つらい」を超えると「面白い」が待っている——そんな発見がありました(笑)。
現地ではどんな発見がありましたか?
やはり百聞は一見に如かず、という言葉の通りでした。写真や資料だけでは分からなかった空間の持つ力を、実際に体感できたのは大きかったです。特に印象的だったのは、同じブランドであっても、展示の仕方や空間づくりによってまったく異なる印象を与えること。そこから、デザインの持つ力と可能性を改めて感じました。
帰国後の報告書のとりまとめは、相当大変だったかと思いますが、どのような点に注力されたのでしょうか?
企業の歴史や背景をしっかり調べたうえで、現地で得たリアルな情報と組み合わせながらレポートをまとめるよう意識しました。特に、デザインに詳しくない方にも興味を持っていただける内容になるよう工夫しました。
さらっとご説明いただきましたが、実際にはかなりの時間と労力を要する作業だったのではないでしょうか?
本当に大変でした(笑)。事前準備で一人20社、帰国後は約80社の中から12社に絞り込んで。報告会までに全体で4回の下打ち合わせを行い、フィードバックを受けながらロールプレイも重ねました。振り返ってみると、100ページ以上あった資料を一人15分程度の発表にまとめる作業は、想像以上の労力でした。
当日の報告会はいかがでしたか?
正直、まだまだ話し足りない気持ちでした(笑)。でも、聞いてくださる方の立場を考えると、あのボリューム感がちょうどよかったのかもしれません。 報告会は、デザインの重要性を社内に伝えるうえでの第一歩になったと感じています。ADIがリブランディング事業をスタートさせてから、社内全体でデザインに対する意識が少しずつ高まってきたように思います。
特に2020年以降は、デザインに対するアプローチに大きな変化が見られるようになりました。以前は、普遍的なデザインを重視していた規格型の集合住宅においても、近年では時代性を意識した提案が求められるようになっています。外構デザインに関しても、過去の実績やコスト面だけでなく、街中で見かけるような洗練された意匠を取り入れる動きが広がっています。
そうした変化を通じて、デザイン思考が少しずつ社内に浸透してきていることを、ミラノサローネ研修での経験を通じて改めて実感しました。
「ミラノサローネ2024」海外研修報告会を開催しました|ADI
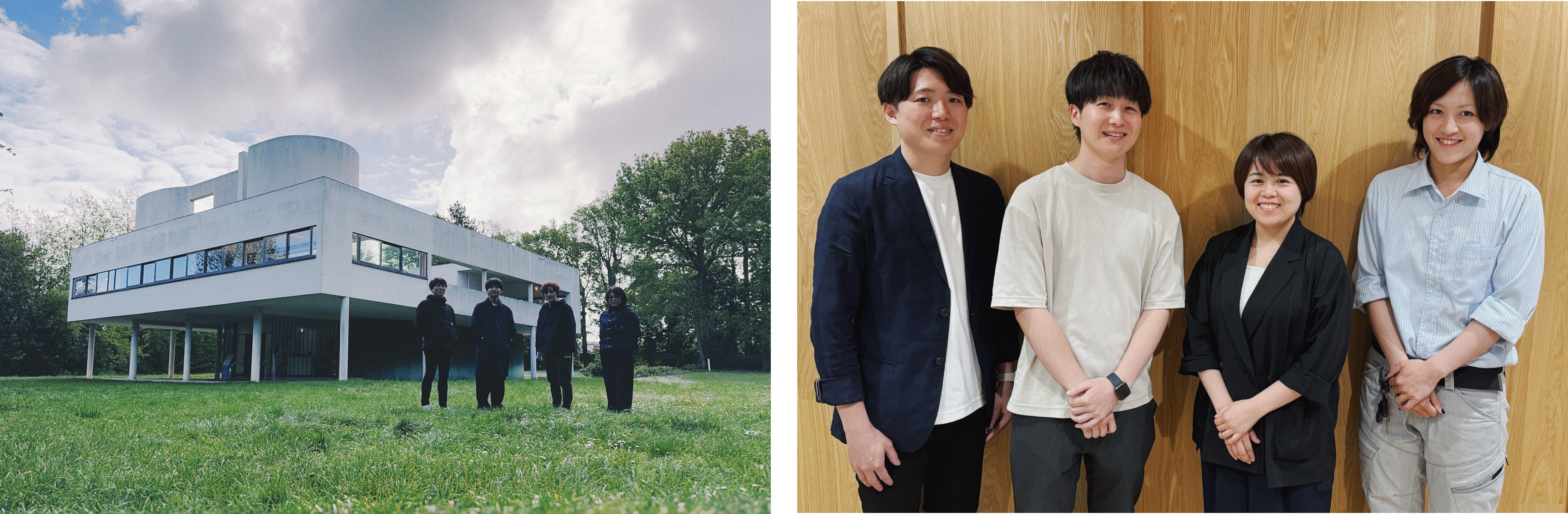
—最後に
風間 三枝からのメッセージ
(ADI 取締役 執行役員 CDO)

ミラノサローネで触れた多様なデザインは、私たちに大きな刺激を与えてくれました。
この経験を一つのきっかけに、デザインを会社の更なる強みとして深化させ、
「美しい暮らし方」を提供しつづけるため挑戦と創造を続けてまいります。

